★あらすじ
著者は余りにも多くのバッタを触り続けたのでバッタアレルギーになってしまった。バッタを素手で触ると蕁麻疹(じんましん)が出るのだ。そこまでして“ものにした”研究成果を著者はやっとの思いで論文に発表することができた。研究テーマは「サバクトビバッタの繁殖行動」について。
著者は海外特別研究員としてモーリタニアのサハラ砂漠で野外調査中、日暮れ後にサバクトビバッタの大群に遭遇する。交尾をしているオス・メス、地中に腹部を伸ばして刺しながら産卵しているメスが山のようにいた。バッタはいつ、どこに現れるか予測できない。研究者と言えこれだけの大群に遭遇することは観察のまたとないチャンスだ。しばらく観察していると、著者は違和感を覚える。そこにいたバッタはカップルとなっているものたちばかりで、あぶれたシングルの雌は見当たらない。シングルのオスもほとんどいない。なぜ、こんなにもカップル成立率が高いのだろうか。著者はそこにバッタの繁殖行動に関する秘密がありそうだと考える。しかし、明日になって明るくなってから改めて観察しようと思ったら、なんとバッタたちは姿を消していた。あれほどの大群だったのに。
ガックリとうなだれる著者。しかし、これが論文のテーマとなる新発見につながる“大発見”だったのだ。カップル成立率の高さや、一晩で消えてしまうカップルたちからバッタたちの繁殖行動が明らかになっていくのだ。だが、その結論に至るまでには長い期間が必要だったのだ。
★基本データ&目次
| 作者 | 前野ウルド浩太郎 |
| 発行元 | 光文社(光文社新書) |
| 発行年 | 2022 |
| ISBN | 9784334102906 |
| 副題 | 自分の婚活よりバッタの婚活 |
- まえがき
- 第1章 モーリタニア編――バッタに賭ける
- 第2章 バッタ学の始まり
- 第3章 アメリカ編――タッチダウンを決めるまで
- 第4章 再びモーリタニア――バッタ襲来
- 第5章 モロッコ編――ラボを立ち上げ実験を
- 第6章 フランス編――男女間のいざこざ
- 第7章 ティジャニ
- 第8章 日本編――考察力に切れ味を
- 第9章 厄災と魂の論文執筆
- 第10章 結実の時
- あとがき 名前とお礼と挨拶と、参考・引用文献
★ 感想
前作の「バッタを倒しにアフリカへ」から七年。前作の紹介は下記の通り。
前作では論文発表前ということで研究内容に関しては詳しく書けなかったとのこと。今作で満を持しての研究発表と相成った次第。前作でバッタに関して興味を持つようになったので、その研究内容も面白く、そしてなるほど!と感心してしまった。
そうそう、今回も前作と同様にaudiobookで拝読ならぬ拝聴したが、語るような文体なのでとても聴き易かった。前作以上に文章が熟れていたんじゃないでしょうか。科学論文とは違うものの、一般向けの書籍にしても「相手に理解してもらうように書く」という基本的な目的は一緒。その意味でとても良い。なにせサバクトビバッタという馴染の薄い対象をメインに語るのだから、読者を飽きさせず、いや引き込むための努力は惜しまないという気合まで感じさせてくれた。しかも、冒頭で「読者を飽きさせないための仕組み」を最初に解説してくれているのだから流石です。
その一つがフィールドワークの中心地となっていたモーリタニアという国の文化や人々の様子の紹介。アフリカ西端の国だけど、この本(前作)を読むまでは名前は聞いたことあるけど、どこにあるかも、ましてやどんな国かも知らなかった。でも今ではなんとなくの親近感まで感じるようになっている。
日頃目にするアフリカに関するニュースって、内戦やら難民、飢餓、そして疫病の蔓延などの話ばかり。しかもざっくりと”アフリカ”としか認識せず、どの国の話なのかもわからずに聞き流してしまっている。それが、モーリタニアってこんな国なのか、いや面白い人たちが多い国だなぁ、などなど、とても興味を持つことができた。Wikipediaや外務省のサイトでモーリタニアに関して調べちゃいましたから。
地道なフィールドワーク(観察・観測・データ収集など)を何年も続け、そこから新たな発見をし、苦労して論文にまとめて発表。ついには各種の賞まで貰ってしまうというサクセスストーリー。前半の地道な努力が伝わってきたからこそ、話に嫌味がまったくない。素直におめでとうと言いたくなってしまう読後感だった。科学することってやっぱり楽しいんだなと再認識させてくれた。期待通りの面白さだった。
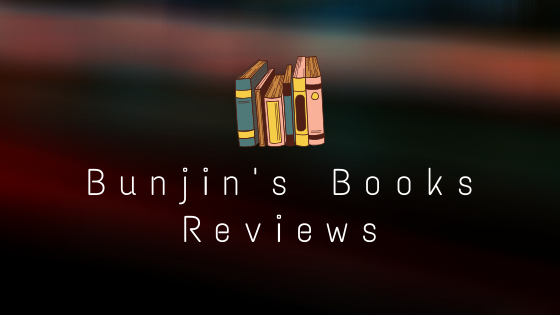



コメント