★あらすじ
本書は日本外交がどのようなものであったか(あるか)を、60の問いと答えという形で概説している。問いは20問ずつに分けられ、戦前編・戦後編・現代編としてまとめられている。
以下、数問をピックアップして紹介する。
明治政府は、対馬藩主宋義達に対し、王政復古を朝鮮政府に通告させた。しかし、朝鮮側は日本からの国書の形式が、日本天皇が朝鮮国王より上位にあることを示すに等しいとして、その受理を拒否した。
この時代から、朝鮮(韓国)や中国、そして他のアジア諸国との関係は良好とは言えない状態であった。そして、それが現代にも言えることだ。
日本語国際連盟を脱退した時の外相は、斉藤実内閣の内田康哉だった。蒋介石と汪兆銘の合作政権は反共反ソであり、対日宣戦を否定しつつ日本との直接交渉によって満州事変解決を打診してきた。かのリットン調査団も日本と中国と双方に対して公正であろうとしており、その報告書は“既成事実”をある程度認める内容だった。だが、内田外相は、「中国は満州(建国)を致し方ない」と考えているのだと判断し、国際連盟に対しても強硬な態度をとり続けたのだ。
冷戦期、アラブ諸国とイスラエルが対立する中、日本は双方に対して中立かつ巻き込まれないように外交を進めていた。憲法九条を有する日本は有事の際も軍事力を用いることはできないからだ。しかし、湾岸危機(イラクがクエートに侵攻)が勃発し、多国籍軍が組織されると、日本も対応を迫られた。
結果として日本は資金提供のみを行う。その総額は130億ドルに上った。しかし、戦争終結後にクエート政府が米国の新聞に感謝の意を示した広告に日本の名前はなかった。日本の“貢献”は全く評価されなかったのだ。以後、日本は資金援助だけではなく、自衛隊の派遣(物資輸送や後方支援など)を行っていくようになる。
★基本データ&目次
| 編者 | 片山慶隆, 山口航 |
| 発行元 | 吉川弘文館 |
| 発行年 | 2024 |
| ISBN | 9784642084468 |
- 日本外交は何を目指すか
- テーマ別60のQ&A
- 戦前編
- 戦後編
- 現代編
- 自由で開かれた国際秩序を求めて
- 外交を知るためのブックガイド
- 第一次世界大戦前の世界勢力地図
- 冷戦期の世界地図
- 主な国際機関本部地図
★ 感想
人口減少、国力低下など、最近の日本に関しては元気のない話が多い。一方で中国と台湾の関係はさらに悪化しそうだし、ロシアはウクライナ侵攻に勢いを取り戻している。そして、北朝鮮は相変わらずミサイルを飛ばし続けている。内憂外患とはこのような状況のことだろう。そんな中でどのように振る舞えばいいのか、「外交」が非常に重要になる。と言いつつ、普通に使うこの「外交」という言葉、実はどういうことを意味しているのか良くわかっていない。そして、日本がどのように「外交」を行っている(いた)のか、歴史を勉強した中で大まかには知っているつもりでいるが、細かいところや歴史的背景、その後への影響になると知らないことばかり。そんな中、本書の宣伝を目にしたので早速買ってみたのでした。
タイトルに「外交入門」と謳っているだけあって、時系列にトピックスを解説している”通史”的な記述となっている。海外との交流といえば、卑弥呼が魏志倭人伝に登場するのが記録として残っている最古のものだろうが、流石にそこから書き出すと歴史の教科書になってしまうだろうから、始まりは江戸時代の終わり、明治の始まりから。
戦前編では、いわゆる「列強」の仲間入りをしたあとの日本が領土拡大・植民地獲得を目的として「外交」を展開している様子がよく分かる。中国・朝鮮に対しては武力や懐柔策を取り混ぜて抑え込みを図り、欧米各国に対しては”陣地の取り合い”を繰り返している。まるで「信長の野望」のようなゲームをしている感覚だ。たかだか百数十年前はこんなだったのかと改めて驚く。
戦後編になってやっと馴染みのある(?)レベルで「外交」が語られるようになったと感じた。戦後の覇権争いや冷戦時代はまだまだ鍔迫り合いの状態だが、概ね平和を維持して経済的発展をしていくための「外交」となっている。
喧嘩をしている(武力にせよ、経済的競争にせよ)相手と”話し合い”をして事を進めていかねばならないのが「外交」だというのがよく分かる。”妥協点”(互いにある程度、利益がある点)を探さねばならないのは本当に根気がいる話だ。
現代編では「外交官って何をする人?」、「大使館と領事館ってどう違うの?」など、外交にまつわる基礎的な説明もしてくれている。その上で最近の外交に関す課題を紹介している。領土問題やら戦争責任・賠償問題、経済協力などなど、日々、ニュースで目にする話が続く。
なんであんな独裁者と対話をしなければいけないのか?と単純に思ってしまうが、国と国(”国”と国際的には承認されていない”勢力”もそうだが)が付き合うとはそういうことなのだろう。絶対的正義だの正しさだのでは語れないものがそこにあることを再認識させられた。
いつの時代でもそうだろうが、「外交」という麺では我々の生きる現代もなかなか難しい状況にあるようだ。そんな中、自分は何をすべきか考えねばならない。そんなことの第一歩になる一冊だ。
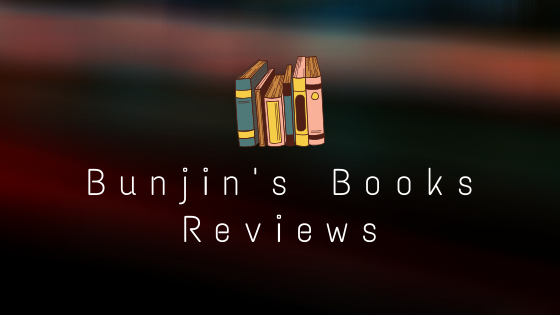





コメント